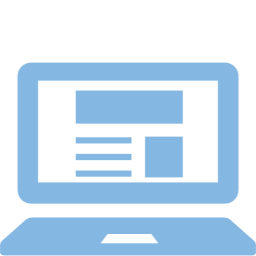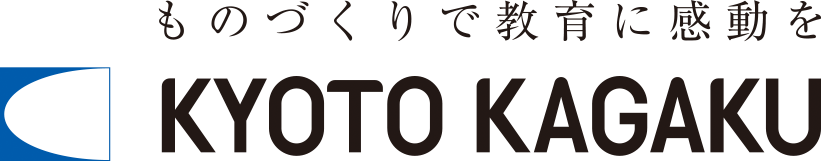- 医学部
- 医学カリキュラム
- 医学生
生涯医師として生きていくための人づくり
2018年に改築を伴うリニューアルを行い、新しく生まれ変わった東邦大学医学部 臨床技能学修センター。 同大学で教鞭をとりながら、センター運営に携わってきた廣井直樹先生、大和田芽衣子先生(看護師)、専従事務員の平井若葉さんにお話を伺いました。

*この記事は「2022年度 医学・歯学教育教材カタログ」に掲載の記事をWEB用に書き起こしたものです。
① 教育の質を向上させるための教員養成

近年、医師として生きていくために、生涯に渡り主体的に学修を続けていくことの重要性が認知されるようになり、教育現場では、旧来型の講義形式の受け身の授業から能動的学修(アクティブ・ラーニング)への転換が急速に進み、考える学びが求められています。
アクティブ・ラーニングの推進や実践能力の修得といった教育改革が進むなかで、「シミュレーション教育」の占めるウエイトは大きくなりつつあります。Pre-CC OSCE公的化も一つの大きな転換点かもしれません。東邦大学の3、4年次では、いずれの学年も約60時間のシミュレーション教育を確保していますが、タスクトレーニングが中心であり、臨床現場に即したシナリオ学修はまだ十分とは言えません。更なる拡充を目指し取り組んでいるところです。課題は「教員を育てること」にあります。
当センターに着任した約10年前からシミュレータを使って学んできた世代が育ち、全体としてはシミュレーション教育に協力的な教員が増えてきたと実感しています。一方で、10年では、満足のいく教育に到達することは難しいとも感じています…適切なプログラム開発と学びのスタンダードをつくることは、時間がかかることを痛感しています。
ところで、教員の資質って何だと思いますか?僕は「医者」としての資質も大切ですが「教育者」としての資質が重要だと思っています。なので、教育を良くしていくためには、我々の教育能力のステップアップが重要なんです。具体的な取り組みとしては、教育能力向上のための学びとしてのFD(ファカルティ・ディベロップメント)を体系化し、その中でシミュレーション教育実践学修の場を提供していくことです。当センターを拠点として、教育者養成の支援を行っています。最近では、参加者も増え、ワークショップ形式のFDが充実してきていると感じています。
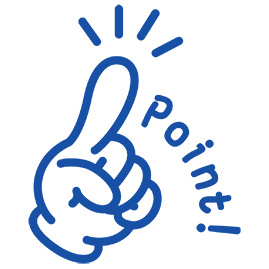
“教員が変わらないと、教育は変わらない”
教育の質を向上させるには、どのように教育の中身を変えていけばいいか?そのために、どのように教員を育てていくのか?をセットで考えながら、教育現場の10年、15年先を想像しながら日々取り組んでいます。
② ICTを活用したアクティブ・ラーニング
オンデマンド発表会
コロナ禍では、様々な方法を使って教育を行う工夫をしてきました。学生の討論内容を共有するための発表会をオンデマンド形式で行いました。これまでの対面授業と異なり「音声スライドを学生が作成し課題を提出してもらう」という試みです。学生から提出された課題スライドをオンライン上で発表し学生同士で評価してもらうとともに、フィードバックもオンデマンドで行うというものです。
結果
オンライン発表会でのパフォーマンス評価では、学生と教員の評価に相違はありませんでした。学生はデジタルネイティブですから、オンラインで資料を効果的に協働して作成・編集するといったことに慣れているのは当然としても、適切なピア評価を行う能力を持っているのには驚きました。
気づきと課題
ソフト面
対面形式や紙ベースでは反応の悪かったアンケートでも、オンラインのフォームに切り換えたら、学生が回答してくれるようになりました。今の学生の傾向としては、自分の立ち位置が安全であることの確証が得られれば前に進める、誰が信頼できるのかを識別しながら生活しているように思います。皆の前で、直接意見を出すのは勇気がいりますが、オンラインであれば安心して意見を出せる様です。
ハード面
以前にも、(学外のプロジェクトで)オンラインを使った模擬試験に携わったことがあるのですが、通信環境の影響を受け0.5秒程度の遅れが生じました。私自身は、その遅れを顧慮すれば良いと考えていましたが、僅かなタイムラグが指導者にとってストレスになっていることがわかってきました。ICTを使った教育の改善は、カメラやマイクはもちろんのこと、通信環境の整備(5Gなど)が課題です。
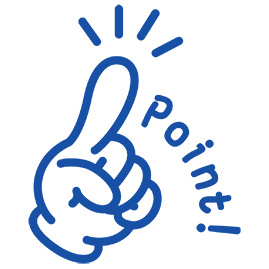
“アクティブ・ラーニングの秘訣は学生のニーズを満たすこと”
アクティブ・ラーニングの前提となるのは、相手が参加してくれて、それに応えること。秘訣はアクティブ・ラーニングによって、学生のニーズを満たすための情報収集や不安を解消する努力を惜しまないことです。学生が楽しいと感じて学べる環境を作ることで、能力を伸ばすことができます。
③ “人づくり”のための箱づくり

センターを使いやすくするための工夫が窺えます
センター運営のヒント

センターのコンセプトは?

「学生が自由に使える場所」をゴールにしています
学生が準備から後片付けまで、学生だけでできるようになれば、自由にセンターを使えるようになりますよね。さらに、学生は主体性を持って楽しく学ぶことができ、教員はサポート役に徹することができます。その結果適切な評価ができるようになります。そんな好循環を生み出していきたいです。
マインド
つながりを大切にする
他施設の教員やシミュレーションセンターとの横のつながりが大切です。様々な教育やシミュレーションセンターを見学することで、新しい情報を仕入れることができ、我々の目指すところが明らかになっていきます。
思いに応える
多くの人たちにシミュレーション教育の重要性を理解してもらうことがセンター運営の鍵です。同時に我々への期待を知り、「その思いに応えたい」という気持ちが現場の原動力となります。
タスク
比較する
他施設の教育やシミュレーションセンターと比較をすること。これによって、東邦大学の特色や強みが見え、足りない部分も見えてくるので、改善がしやすくなります。
情報を発信する
自施設の魅力に気づいていなくても、すでに特色を持っているケースが多くあります。取り組みを「情報発信」する準備の過程で、自施設の特色を発見し整理することができます。
マネー
予算を集約する
シミュレーションセンターを使って実施する授業や試験などの予算をセンターに集約できるシステム作りにより、有効に教育資源を増やすことが可能になります。
補助事業の活用
補助事業を活用したプロジェクトへのチャレンジは、自施設のステップアップのきっかけとなります。「二歩・三歩先の未来を見える化」する作業は、その後の教育プログラムづくりのベースになります。
「患者さんが亡くなるときに、この先生でよかったと言ってもらえる医師になりたい」と話す廣井先生。自然体でセンターの運営をこなす平井さん。そして、シミュレーション教育に精通した大和田先生を迎え、新しい一歩を踏み出した臨床技能学修センターの今後が楽しみです。
 |
廣井直樹 先生 東邦大学医学部 医学科 教授 医学教育センター長(教育開発室長) |
|
ご経歴 1991 年 東邦大学医学部卒業 第 85 回医師国家試験合格 東邦大学医学部付属大森病院研修医 1992 年 東邦大学大学院医学研究科博士課程入学 1998 年 博士(医学)取得 1999 年 米国国立衛生研究所留学 2001 年 ドイツデュッセルドルフ大学留学 2002 年 東邦大学医学部内科学第一講座研究生 2003 年 東邦大学医学部内科学第一講座助手 2007 年 東邦大学医学部内科学講座(大森)糖尿病・代謝・内分泌科講師 2012 年 東邦大学医療センター大森病院総合相談部部長 2013 年 東邦大学医学部教育開発室(医学教育センター)教授 2018 年 東邦大学医学部医学教育センター長 日本医学教育学会 医学教育専門家 日本内科学会総合内科専門医 日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医・指導医 日本糖尿病学会専門医・指導医 |
※ご所属・役職は掲載当時のものです。